猫が主役の竹本一家(1) たけもとのぶひろ
2018年6月11日

1 猫ファミリーの誕生――東京編
官憲に追われる逃亡生活、逮捕されてからの拘禁生活、あわせて17年余りの間、帰る家はなく、あって当たり前の生活がなかった。浦和拘置所を出てからも、数年のあいだは安住の地を求めてアパートを転々とした。漂流というか放浪というか、我が身を寄せる岸辺がなかった。いつどこへでも行くことのできる自由の身になったとはいえ、自分一人が独りだけで自由に生きることなど土台無理な話であることくらい、ちょっと考えればわかることなのに、普段はそのことをできるだけ考えないようにして、なんとかしのいでいた。大都会でただ一人、我が身ひとつが思うに任せない、その、あるがままの情けない自分を前にして、秘かに、しかし真っ正面から、向き合わざるをえないときが、一年に一度必ず来る。長年の間、それがぼくにとっての正月だった。自由の身になってからも、正月は苦手だ。苦手意識は今も続いている。
ところが、何事にも例外というものはある。あれは、出所して7年目だったか8年目であったか、東急二子玉川線の駒沢大学駅から歩いて10分くらいのアパートに住んでいた頃の、正月6日の出来事だった。
アパートは三階だったと思う。たまたま外を見たときに目に入ったのだが、ベランダの手摺りの上に、青い鳥が止まっている――あたかも部屋の中を覗くというか、窺うかのように、こちら向きに止まっているのだった。飼われていた家の鳥籠から何かのはずみで外へ飛び出してしまったのではないか。外を飛ぶうちに飼主の家がどこか分らなくなって、どうしたらよいか途方に暮れているのではないか。ひょっとしてこの家が飼主の家かもしれないと、中を覗いているのかもしれない。真冬のことゆえ長居は無用、身体は冷えるし、腹は減るし、このままだと凍えて死んでしまうのではないか。
放っておけない。ガラス戸を開けた。小鳥は迷うことなく部屋の中に飛んで入ってきた。図鑑にバイオレットインコとある、その青い小鳥は、ぼくの部屋から出て行かない。居着いてしまうつもりらしい。二間しかない狭いアパートの中だけど自由に飛んでよいことにした。所構わず白いうんちのようなおしっこのようなものを排泄したけれど、いちいち構うことはない、適当に掃除してやればよいだけのことだと腹をすえた。気が向くと、ぼくの頭の上に止まったりもしてくれる、そこまで懐いてくれることが嬉しかった。もちろん名前をつけた。山本周五郎著『天地静大』の登場人物の名前をお借りして「なほ」ちゃん、と。雄か牝か、分らなかったのだけれど。(注、このことは以前にも書いたのだが)。
「なほ」ちゃんとは何か月いっしょに暮らしたであろうか――楽しい日々が続くなか、何がきっかけであったか、今となっては記憶していないけれど、何の前触れもなく不意に、「つよし」との日々が思い出のなかから出て来て眼前に広がる思いがした。
懐かしかった。栃木県足利市のそば屋「さらしな」の店員と身分を偽って潜行していたときに出会った、後脚の不自由なちっちゃな黒猫。以後、逮捕されるまでのおよそ8年間、ぼくはつよしを連れて逃げた。(注、この「つよし」のことも以前に書いている)。黒猫と一緒の逃避行は官憲の知るところとなり、それがためにいっときは別々の道を逃げたこともあったのだが。その「つよし」のことは、普段はあまり思い出さないことにしてきた。思い出の回路に入ると、どうしても思いは沈んでいく、時と場合によっては、悲しみの中にはまり込んで出てこれなくなったりする。普段は、心の中にある「思い出の箱」にしまってあり、滅多なことでは出さない。鍵をかけて大事にしている。
その「つよし」が、しまってある箱の鍵を開けて眼前に現われ、語りかけているように思えた。「思い出の箱はもう要らないんだよ。ぼくという猫もぼくでない猫も、姿形が違うだけで、本当は同じ猫なんだ。だって飼主が同じ人間なのだから同じになっちゃうよ」と。
猫をもらって一緒に住みたいと思った。何年もの間、無理にせき止めてきた思いが一気にあふれ出るかのようであった。そのときの自分の、求めてやまぬ気持ちには切なるものがあったと思う。
しかし、バイオレットインコの「なほ」ちゃんが住んでいるところに猫を連れて来ると、猫がインコを食べてしまうのは必定、それはできない。猫をもらってくるには、その前にインコの「なほ」ちゃんの嫁ぎ先を見つけないといけない。
さて困った。思案投首のところへ、日頃から治療してもらっていた近所の鍼灸整体院の先生が助け舟を。自分の患者のなかにオウムを飼っている人がいる、とっても大事にしている、可愛がっている、相談してみては、と。会って相談に乗ってもらう。意外や意外、自分が引き取る、と。インコも同じオウム科の仲間、一羽も二羽も飼う手間は同じ、一羽でいるよりも仲間ができた方が寂しくなくていい、などと言ってくれる。世の中捨てたものではない、と身に染みて感じ入った。
駒沢のアパートはペット禁止だった。「なほ」ちゃんは小鳥だし目立たないが、猫の鳴き声は隣り近所に聞こえてしまう。こっそりと隠れては飼えない。はじめから「ペット可」をうたっている住まいを探さなければ、そして肝腎の猫を譲ってくれる人を探さなければ。
猫といっしょに暮らす、本来の人間らしい生活を、これから始めることができるのだ――
そう思うと自ずから “よし、やってやる” という気になるのだった。
猫といっしょに本来の人間らしい生活、などと書くと、読む側は妙な気がするかもしれないが、人間といっしょに本来の人間らしい生活を求めて懸命の努力をするとせんか、その苦心惨憺たるや筆舌に尽くせぬものがある、しかも成功するか否かは保障のかぎりではないと思うが、いかがか。
かと言って、インコの「なほ」ちゃんとなら、いっしょに理想の人間らしい生活を求めていけるかというと、なかなか難しい。相手は鳥類だし、こちらは哺乳類だし。頭も心も身体にしても、相互理解ができかねるほどに違い過ぎる。
そこへいくと猫とか犬とかは――逃走中にある農場で世話したことのある豚や牛も、飼ったことはないが馬とか象も――人間と気もちを通わすことができると思う。人間は抱っこしたり撫でてあげることができるし、彼らだって人間に甘えたり、ときには怒ったりすることもできる。お互いを思いやり・高めあい・励ましあい・慰めあって生きていくことができる、そういうふうに “共同生活” ができるように創られているのではないか。同じ哺乳類だもの。
とまれ、猫とぼくがいっしょに住む家を探そう。それよりもなによりも、猫そのものとの出会いがなければ話にならないのだが。
もともと不案内な東京のこと、住まいを探すと言っても、方角さえ分らない余所者ゆえに、いつも苦戦する。結局は、同じ東急二子玉川線の駅の近くの不動産屋を当たっていくしかない。小鳥ではなくて猫だし、身体も大きくなるわけだから、二部屋のアパートでは狭いだろう。理想を言えば、廊下があったほうが、走り回れるし、猫は喜ぶのではないか。駒沢大学駅の次の桜新町駅の近く、歩いて10分くらいの深沢地区に、程よい物件――マンションの二階三室廊下つき――を見つけた。すぐに引っ越した。
肝心なのは、その中でいっしょに暮らしてくれる猫である。まさか「ネコください」なんてステッカーを貼ってまわるわけにはいかないし。猫に理解のありそうな友だちに声をかけてお願いするしかない。
「つよし」が雑種の黒猫だったから、貰うのはどうしても雑種の黒猫でなければ、と思いつめていた。雑種ということは、要するに「野良猫」であって、ペットショップで売られているような猫ではない、という意味だ。お願いするときも、だから、「雑種の黒猫を飼いたいのです、お願いします」とくり返した。
友人の親切が実を結んでくれるまでに、そんなに日にちがかからなかった。知り合いの夫婦が子猫を捕まえて、しっかり確保している、と朗報があった。その夫婦というのは、東京農大を卒業したのち、まともな野菜を作って宅配便で消費者に届けて食べてもらおう、と二人して百姓を生業とすべく目下挑戦中だという。賢い消費者運動とか、無農薬有機農業とか、消費者自給農場とか、そういう流れのなかで真っ当に生きていこうとしている人たちなのではないか――そういう印象を持った。
さらに友人によると、おふたりはたまたま捨て猫に出くわしたりすると、どうしても見て見ぬ振りができない性分らしく、ついつい拾ってしまうという。ぼくが貰おうとしている猫は、あろうことか、公園のトイレの屋根の上に捨てられていたという。善意に解釈すれば、
①屋根の上だと、猫は怖いからにゃーにゃー泣き叫ぶだろう、
②通りがかりの人間は誰だって気づいてくれるに違いない、
③なかには可哀相にと哀れんで拾ってくれる人がいるのではないか、ということだったのではないか。
それが、ほんとうに捨てた人の思惑だったとしたら、その思惑通りに、猫は拾ってもらえたのだから、結果オーライと言えなくもないけれど、なにかしら釈然としない、後味の悪さみたいなものが残る。
だって、たまたま、心の温かい、思いやりの深い人が通りがかってくれたから良かったけれど、泣けど叫べど、誰も来てくれなかったら、どうなっていたことか。非情かつ無責任、の誹りは免れないと思う。
まだある。捨てられた子猫はトイレの屋根の上で泣いている。怖がっているのだ。どうしたって、屋根の上によじ登らなければ、捕まえられないし、救出できなかったと思う。しかし、どうやって? そこまでやってくれる人がいたのだ。「惻隠の情」の人は、今もこの世に生きているのだ、と身に沁みて思った。
子猫を連れてきてくれたのは、友人だった。果たせる哉、黒猫だった。捨てられていたのだから、立派な野良猫だ。念願がかなえられたぼくの喜びは、喩えようがなかった。
お尻を見ると、雄猫であることの証しがちゃんと付いている。「五郎」と名づける。貰える猫が雄か牝かわからなかったし、あらかじめ名前を考えてはいなかったが、それでも即座にこの猫は「五郎」なのだ、と思った。雄猫だったことで、「つよし」の生まれ変わりかと思ったりもした。でも、五郎はこれから五郎の生涯を生きていくのだ、と強く思った。
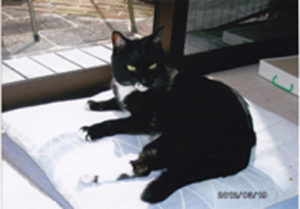
人間の名前のように聞こえるかもしれないが、そもそも人間も猫も違いはないと思っているのだから、これでよいのだった。
黒猫でなければならない、という強いこだわりも、満たされた。「つよし」は全身が真っ黒の、正真正銘の黒猫だったが、「五郎」は百パーセントの黒猫ではなかった。ひっくり返して腹を見ると白かったし、顔の下の胸の辺りはいつも三角の白い前掛けで覆われていた。もう一つ、上唇の片方に、ほんの少しの面積、白い毛があった。細かいことを言うと、こういう猫だけれど、だれが見ても一見して黒猫と思うに違いない、そういう猫だ。
それよりも何よりも、初めて会ったときなんか、両手の中に丸くなってすっぽり入ってしまうほど、小さかった。小さいし、丸いし、黒いし、可愛いし、その魅力は言葉で言えないほどだった。なにしろ嬉しかった。ここにこうして、ぼくと五郎の猫ファミリーが誕生したことが、である。
深沢での最初の一年は、ぼくと五郎の二人だった。猫は寝るのが仕事だというが、いつもぼくの膝の中で丸くなっていた。起きているときは、三つの部屋と廊下を走りまわっていた。クロネコヤマトのおっちゃんが配達に来ると、必ず玄関に迎えに行く。まだ子供で好奇心が旺盛なためか、人間好きなのか。おっちゃんも五郎が好きらしい。五郎を間に三人でとりとめもない話をして過ごすひとときが楽しかった。
だけど、愉しいだけではなかった。肝をつぶすような出来事に遭って死ぬほどの思いをしたこともあった、それも一度ならず二度も。五郎がマンションのベランダから落ちたのだった。ベランダは低い壁で囲ってあって、その上に丸いポール状の手摺りが渡してあった。それに乗っかると滑って地面に落ちてしまわないかと心配でならず、いつも注意していた、 “ベランダの手摺りの上に乗ったらあかんよ、トンするよ” と。
なのに、二回落ちた。しかも、運の悪いことに、二回とも夜だった。夜の暗闇のなかで黒猫の五郎を捜し出すということは、真っ暗なところで黒いものを捜すことなのだから、容易ではない。ニャ~とかなんとか鳴いてくれればいいのだが、黙ってじっとしている。この庭のどこかで、じっとしているに違いない。事の成り行きにびっくりし、黙って震えているのではないだろうか。 “怖いなぁ、どうしよう、お父さん早く見つけて!” と。
焦った。囁くような小さな声で “五郎! 五郎!” と呼ぶしかない。見えないのだから、ローラー作戦よろしく、地べたを這いずり回って五郎を探り当てるしかない。視覚が役に立たない以上、触覚に頼るしかない。
マンションの家主は一階に住んでおり、五郎の落ちたところは大家さんの庭だったのだ。他人の所有地に無断で入り込んでネコを探しているのだから、怒られても仕方がない。ここは、謝って謝って、暗闇のなかの五郎を探し出さなければ……。
2~30分もかかっただろうか、長く感じただけで、ほんとうはもっと短かったのかもしれない。ようやく五郎を探り当てて抱きしめた。そのときの喜びは喩えようもなかった。五郎もよほど嬉しかったのだと思う。爪を立ててしがみついてきたのだから。
五郎と暮らすようになって一年くらい経った頃だったろうか、はたと気のつく機会があった。 “ああ、そうか、五郎もこれだけ大きくなると一人前の雄猫や。連れ合いをもらってあげないと可哀相かもな ” と。
こういうときに頼れるのは、あの東京農大卒の百姓志願のご夫婦以外にはいない。あのときお世話になって以降、お二人の野菜宅急便のお世話になっている。当初は東京の世田谷だったのが、しばらくして愛知県の渥美半島に農地を求めて移住、そこを本拠に、百姓を営んでおられたのであるが……。ちょっと遠いなぁ、と躊躇うところがあったけれど、相手の迷惑は承知の上で、ままよとお願いした。“「野良の黒猫の牝」が見つかったら、五郎の連れ合いとして迎えて、いっしょに暮らしたいのです、五郎のときに被ったご親切に甘えるようで心苦しいのですが、どうかお世話してもらえないでしょうか”と。
電話口の妻女は “いいですよ、見つけてあげますよ、すぐに見つかりますよ” と言わんばかりに気安く、こちらの願いを聞き届けてくださる。まるで、自分の目の届くところに、すでに猫がいるかのような、自信ありげな口振りだった。
何となく感じていた手ごたえの通り、やっぱり猫はいたのだった。翌日だったかその次の日だったか、彼女から電話があった。 “ いましたよ! うちの納屋の高い梁の上に座っていたの、ときどき。黒猫です。きっと女の子だと思ったけれど、念のために碓かめました。やっぱしメス猫でした!”
新幹線で東京駅まで連れて行ってあげる、とまで言ってくださる。こういう親切がこの世の中にまだあるなんて、それに見合うような、その恩義に報いるようなお礼の言葉というものがあるだろうか。
八重洲口で待ち合わせて、人混みの中で黒猫をバスケットごと引き渡してもらう。こういう状況では人間よりも猫の事情が優先する。長旅の疲れや不安や恐怖からくる猫のストレスを考えると、一刻も速く深沢の自宅に帰って籠から出してあげなければ……。お礼もそこそこに、帰りを急いだ。
そして、マンションの玄関に駆け込む。いつものように、五郎がドアに身を押しつけんばかりにして待っている。猫を籠から出してあげる。真っ黒のかたまりが勢いよく出てきて、びっくりしている。やわらかな、ふわふわの毛がまぁるくふくらんでいる。目が大きくて、鼻が低い長毛種。ペルシャ猫と日本の野良猫との雑種らしい。「にぃ~子」「二~子」と呼ぶことにする。ぼくの家に来てくれた二番目の猫だから「二~子」。迷わず直ぐに決めた。
もちろん、五郎もびっくりしている。 “いったい何や? 何やこれは?” と。
貰ったばかりのとき、ほんとにちいちゃかった五郎に比べると、二~子のほうが少し大きいかもしれない。でも、生まれてひと月くらいだったのではないか。

ふたりはすぐに仲良くなった。いっしょにじゃれて遊ぶし、ひとつの丸になって寝るし。
しかし、五郎は初っ端から二~子に参っていたのではないか。なにしろ二~子はうけぐちの美形だし、グラマーだし、歩くのだってモンローウォークさながらだったのだから。
五郎だって捨てたもんじゃない、短毛種だから脚が長く見えてなかなかかっこいい。穏やかだし、人懐っこい。でも、洋猫の攻撃本能は苦手だったと思う。ふたりで遊んでいるときなんか、よく見かけたのは、二~子が五郎を追いかけ回している情景だ。ニ~子は低い構えから五郎に飛びかかってネコパンチを喰らわせる。五郎は後脚で立ち上がって、二つの前脚を振りあげて “やめて やめて” と言っている。
そういうことは間々あるのだけれど、五郎は、二~子のことが好きだし、彼女の賢さには一目も二目も置いていたと思う。ふたりともネコジャラシが大好きで、遊んであげると、もう夢中になって追いかけまわす。散々遊んで、もうお終いとなったときは、必ずネコジャラシを遠くに投げてやるのが決まりだ。五郎の次は二~子、二~子の次は五郎、と順番に。ふたりとも、走っていって口に食わえて、ぼくのところに持って来る。
あるとき “待てよ” と思った。二本のネコジャラシを同時同方向に投げたら、彼らはどうするだろうか、と。やってみてびっくりした。五郎は、二本のうち一本を食わえてぼくのところへ持って来る。ところが二~子は、違った。二本のネコジャラシのうち一本を口に食わえて、二本目のネコジャラシのところへ持っていって、そこで二本のネコジャラシを一つにまとめて口に食わえ直して、ぼくのところへ持ってきたのだった。 “ほぉ~っ!” と思った。その二~子を、五郎も見ている。 ”これは参ったなぁ!” と感じ入ったに違いないが、”ぼくは一本でいいんだ、あとの一本は関係ないよね” という目でぼくを見ている。
ぼくと五郎のときも、二~子が来て三人になってからも、深沢の竹本猫ファミリーはいつだって元気だったし、面白がって生きていた。猫も人間もみんな若かったから………。
次回は、2 竹本猫ファミリーに新顔参入――京都編















