たけもとのぶひろ(第62回)– 月刊極北
番外編(上)
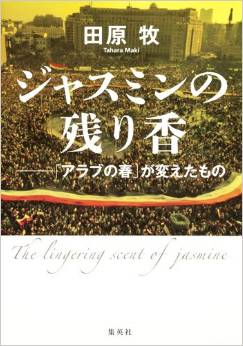
田原牧著『ジャスミンの残り香――「アラブの春」が変えたもの』を読む
■メフメットとの出会い・「周回遅れ」世代の政治意識
著者の田原さんは本書「まえがき」の最後にこう記している。「なによりトルコの友人、故メフメット・イソットがいなければ、私はアラブ世界の戸口に立つこともできなかった。鎮魂歌の代わりに、この作品を彼に捧げたい」と。田原さんにとってメフメットの存在がいかに決定的であったか、出会いのところからみておきたい。
30年近く前、田原さんは初めての海外渡航でシリアのダマスカス――「パレスチナ解放人民戦線(PFLP)」の事務所がある――を目指していたらしい。「自分の目では一度も見たことがない、生の革命運動の現場を訪れてみたい」と。何かの事情でアテネからダマスカスへの直行便は飛んでおらず、しかし、隣国トルコからなら入れるだろうとの情報を得て、イスタンブールへ飛んだ。そのイスタンブールの、たまたま立ち寄ったイスタンブール大学の構内で、生涯の友・メフメットと出会ったのだという。
当時、メフメットは毛沢東主義の急進左派組織のメンバーだった。田原さんも高1以来の新左翼系学生運動の活動家。大学時代は大手政治セクトとの抜き差しならぬ敵対関係をしのいできている。ふたりは目が合った。トルコ映画の話で盛り上がった。メフメットが田原さんのピンチに救いの手を差し伸べてくれた。往時を懐かしむかのような文章がある。
「活動家は国境を超えて、同類の匂いに敏感なのだろう。数日後には、近くの安酒場でナツメヤシが原材料のラク(アラク)の杯を重ねていた」。
このときから友情は途絶えることがなかった。「出会ってから十余年後の1990年代後半、新聞社の特派員としてカイロに常駐していたころ」も、「特派員を終えてカイロを離れた後も」彼らは互いに連絡を取り合っていた。著者の紹介でパレスチナ人のマルワーンが加わり、友だちは三人になった。
彼らは世代が同じなだけでなく、反体制運動の体験をも共有していた。価値観や感覚なんかについても、理屈ぬきで通じ合うものがあり、国境の隔てを感じることはなかった。著者は、たとえば次のように語っている。
「この三人に通じるものがあったとすれば、それぞれの生きてきた場所では、負ける闘いしか知らなかったことかもしれない。悲劇にすら至らなかったということだ。三人とも反体制運動に身を投じたが、その隆盛期には乗り遅れた。」
「1960年代後半から70年代初めの熱い季節はとうに去っていた。そうした季節のツケだけを回されるのが「周回遅れ」たちの定めである。明るい未来など望みようがなかった。
それでも、八方塞がりの世界に楯つかなければ、自分が消え失せてしまうかもしれないという焦燥感が政治への興味をつないでいた。」
これらの文章を読んでいると、歴史という名のバスに乗り遅れて、置いてき放りをくらったような、そうして誰にともなく “チェッ” と舌打ちするしかない、著者たちの、いまいましい気持ちが伝わってくる。さらにいまいましかったであろうことは、自分たちはただ間に合わなかっただけなのに、それだけでなにか “負い目” という名の荷物を背負わされたかのような、おまけに、その荷物を担いでいますぐに駆け出さずにはおれないような焦りまで感じさせられている――なんや、これは! というか。
三人が三人とも、新左翼多数派の革命運動――その前衛主義・エリート主義・教条主義・英雄主義・自己犠牲ナルシズム――に取り囲まれていた。その囲いの外に出て、自らの時間と空間を取り戻す、そのときこそが、かの “負い目や焦り” から脱して、自由へと放たれていくときであった。著者は、自身の言葉でこう述べている。
「(三人に)偶然にも共通していた志向は権力奪取の教条から脱した、世間の多数派とは一線を画した居場所づくりという発想だった。」「むしろ、多数派の秩序の外にこそ自由の風が吹き、心に落ち着きをもたらす空間が開かれている。」「多数派にこだわるより、そうした価値観の異なる居場所が広がっていくイメージ」等々と。
■革命
これでいくと、田原さんたちにとって大切なのは、権力奪取とか多数派形成とかではなくて、人びとの間に自由の風が吹く、そういう居場所が広がっていくこと、それ自体であった。革命とは勝つか負けるかの権力闘争に勝利して理想を実現すること――みたいなのが一般的イメージであるが、そんなものではないということだ。
権力奪取闘争だからといって、権力は客語にとどまることができない。主語として君臨する。反権力側のいう権力奪取闘争といえども、権力闘争たることをまぬがれない。権力こそが革命の主体だということにならざるをえない。だとすれば、闘う人びとの立場はどうなるのか。「革命の客体」「動員対象」以外のものではない。
しかし、闘う人びと・生身の人びと・市井の人びと・の一人一人が、あくまでも「革命の主体」でなければ、おかしいのではないか。
それだけではない。革命の勝利によって理想を実現する、というが、人びとの艱難辛苦の献身的闘いがあって、その結果、実を結ぶのが革命の理想というものなのか。あらかじめ約束されている「革命の理想」が、約束通り実現するか否かは、結果次第ということなのか。違うだろう。革命は結果ではなくて、過程であろう。生身の人びとが闘いのその時その場で、その人自身が変化・変身していくプロセスなのではないか。
ここからさらにつきつめて田原さんは、自分自身の変化、社会の変化、そして変化の過程としての革命、ということを関連させつつ、思索を深めている。例えば、以下の通り。
「人はなにより自らの存在を確認するために怒らなければならない。(中略)理由は、尊厳や怒りこそが自分の存在を自覚させ、その精神の成長を促すからであり、そうして人が変わることが社会を変える可能性の基礎になると思えるからだ。」
上記に、「怒らなければならない」「尊厳や怒りこそが自分の存在を自覚させ」とある。とりあえずは社会の不条理にたいする怒りであっても、怒りは、その不条理な社会を構成してきた旧い自分自身に対する怒りとなって、自分のもとに跳ね返ってくる。旧い自分に対する怒りは、旧い自己との訣別のバネとなる。人びとはこのようにして、一人一人が自分自身を変えていく自己変革のプロセスを闘わざるをえない。その闘いはパスするというのであれば、社会を変えるなどという大それたことはできる相談ではない。
同じ主旨のことを別なふうに論じているところがある。そこを引用し、再論したい。
「革命の意味はその結果ではなく、過程にこそ宿る。そうした思いが募っていった。それは革命の主人公である民衆一人一人の変化だ。人間が強くなることことと言い換えてもよい。(中略)革命が理想郷を保証できないのであれば、(中略)いつでもそれを覆せるという自負を持続することではないのか。個々人がそうした精神を備えていることこそ、社会の生命線になるのではないか。」
革命の意味は結果ではなくて「過程」にある、という。なぜか。革命は、人間および社会における「変化」の実現を目指すからだ。そして、その「変化」は、「過程」のうちに実現され、かつ認識されるしかないからだ。加えていえば、その「変化」「過程」には終わりがない。したがって、「革命」は永続する。永続しないわけにいかない。あらかじめ永続を断念ないし抑止した “革命” は革命ではない。
変化を永続させることは容易ではない。なぜ、容易でないか。革命の過程とは、なによりもまず、「革命の主人公である民衆一人一人の変化」でなければならないからだ。人びとの一人一人が変わらないのに、社会が変わるわけがない。人間は変えることができなくても、社会は変えることができるなんて、あるはずがない。
変化・革命の永続が必然なのは、ひるがえって考えてみると、不条理の永続が不可避だからだ。だとすれば、「革命の主人公」には、「いつでもそれを覆せるという自負」の持続が要請される。民衆の一人一人が「強くなること」が、とりもなおさず「社会の生命線」である、と田原さんは説いている。
以上にみた田原さんの言説は、革命観の革命、あるいは、もう一歩ふみこんで「不服従」革命の提言、というふうに表現してよいのではないか。このネーミングだと形容矛盾めいた印象があり、適切さを欠くかもしれないが。
■広場
その人その人の自己変革について田原さんは、「社会を変える可能性の基礎になる」と書いている。この確信に至るには、「アラブの春」の予感のなかでタハリール広場(2011.1.25)へと駆けつけた、そのときの体験があるのではないか。「歴史には通ってみなければ分からない道というものがある」という自身の声が、その時に聞こえていたのかどうか。彼の迫力が伝わってくる一文を次に示す。
「三年前の光景を想起してみた。独裁政権が崩壊する瞬間を目撃しようと、カイロに駆け込んだのは、ムバーラクの退陣が発表される直前だった。無理矢理、会社の勤務にすき間をつくり、止める上司を説き伏せて自費で現地に向かった。すでに政権はぐらつき、混乱が混乱を呼び、カイロ行きは欠航便が相次いだ。
革命が起きそうだ。盤石だと誰もが信じていた独裁政権がひっくり返されるかもしれない。その瞬間を世界は固唾を呑んで見つめていた。
(中略)革命は自分にとって、誰ひとり実物を見たことがない中国神話の麒麟のようなものだった。その実物がようやく見られるかもしれないと考えると、いてもたってもいられなくなっていたのだ。」
そして著者は見た。見るであろうと予感した以上のものを見たのではないか。その現場がタハリール広場であった。田原さんの体験した広場を引用する。
「タハリール広場での闘いは、(中略)不条理に対する怒りを表出することで、独裁政権下では存在しえない自己の尊厳と人生を奪還する。さらにそこを終着駅とせず、永続的に抵抗する精神を持ち続ける。それがタハリール広場に集まった青年たちの心情だった。その叛逆が倫理的な自治空間を形成し、むろん継続されなかったとはいえ、市民たちの心を変えていった。」
先に「社会を変える可能性の基礎になる」とあった叙述は、ここでは、「むろん継続されなかったとはいえ」「その叛逆が倫理的な自治空間を形成し……市民たちの心を変えていった」というふうに現認されている。
independentな一個の自分の確立は、革命の欠くべからざる必要条件である。しかし、それだけでは十分ではない。加えて、見たこともない新しい空間、広場を切り拓かなければ。
そのことを、著者は次のように書いている。
「タハリール広場には何者にも寄りかかれない不安と、力強く込み上げてくる解放感が漂っていた。そこには自分が何者で、どこに立っているのかをつかみ直す機会が潜んでいた。(中略)そして、自分たちが切り拓いた見たことのない新しい空間でこそ、出会ったことのない自分にも出会えるのだ。」
見たことのない新しい空間! 出会ったことのない自分!_____不条理に対する怒りから出発する不服従の抵抗に終わりはない。著者の革命論は、そういうことではないのか。
■「革命」は徒労だったのか?
以上は、著者の革命観をぼくなりの仕方で概括したものだ。最後に触れておきたいのは、革命に関するこの言説の底流に流れているメイン・テーマについてである。そのことを、著者は「ひとつの宿題」と表現しているのだが……。次の引用文をみてほしい。
「同胞団政権に代わる軍政に等しい暫定政権下では、三年前の「革命」で一掃されたはずの旧独裁政権派がたちどころに復権し、かつての警察国家へと時計の針を急速に逆回転させた。カイロを再訪した2014年1月という時期は、その悪夢への回帰の渦中に当たる。
このとき、私はひとつの宿題を携えてカイロの街に立っていた。それは「『革命』は徒労だったのか」という問いだ。どこか身もフタもない響きがあるが、他人事とも割り切れない思いがあった。」
「宿題」の問いは、一言をもって問題の核心をあらわにしているだけに、たしかに身もフタもなく聞こえる。しかし同時に、同様の流儀で著者がこの問いに対して用意していた答えは、 “徒労だなんて! 徒労だったはずがない!” というものだったと思う。
ただ、それにとどまらない。この問いと答えには「他人事とも割り切れない思いがあった」との著者の述懐がある。
この部分は、本書が捧げられているメフメットに関わっているのではなかろうか。実はメフメットは、エジプト革命の7カ月後に病死している。生前、彼の最後のメールについて著者は次のように記している。
「最後にメフメットから送られてきたメールには、「エジプト人の勝利はすばらしい。でも、本当の闘いはここからだ」と書かれていた。彼は決して楽観的ではなかった。どんなに派手な闘争でも、それを担う人間たちが本当に試されるのは一敗地にまみれてからだ。」
メフメットは言っている。勝利の後に敗北が続く、本当の闘いが始まるのはここからなのだ、と。この言葉が、結果的には、田原さんに宛てたメフメットの “遺言” となった。
「エジプト革命」は革命本番へのとば口を開いてくれたのだ、功労の名に値することはあっても、徒労だなんてとんでもない――田原さんはメフメットとともに、そういう認識だったと思う。だとすると、2014年1月のカイロ再訪は、ふたりのこの認識を検証する旅だったのではないか。他人事であろうはずがない。
現場検証とか事情聴取というと警察めくが著者は、かつての恩師や友人など幾人もの「革命」の当事者たちに直接会って話を聞いている。そのうち本書で紹介されているのは、カイロ・アメリカン大学に語学留学していたときのアラビア語の教師ラグダ・エサーウィ、精神科医で年上の友人アリー・シューシャーン、地元カメラマンの友人ウサーマ・ハムザの三者の証言だ。いずれも捨てがたく魅力的だが、ここではアラビア語の恩師ラグダの証言を引用する。それだけで完結した一編のエッセーとして成立していると思う。だから、引用としては長文に過ぎるかもしれない。が、許してもらう。解説はしない。
ナイル川の中州ゲジーラ(島)の端にあるオープンカフェで。
――唐突に2011年2月の「革命」を予想していたかと聞いてみた。すぐさまラグダは「まったくしていなかった」と、きっぱり答えた。
「ムバーラクが辞任するその日まで、エジプトはずっと変わらないと諦めていた。ムバーラクが辞任した2月11日くらい嬉しかった日はない。自分のこれまでの人生で、最も美しい一日だったと断言してもいい」
そしてこう続けた。「あの日々は奇跡だったのかもしれない。人びとの良心が他の人びとの良心を呼び覚まし、それがどこまでも連鎖していくということを初めて知った。いまはあのときと正反対だ。不信が不信を、犠牲が犠牲を生んでいる」
それならば、「革命」などなかった方がよかったのではないか。突き放したようにそう尋ねると、言下に否定した。いまの状態がどれだけ酷くても、「革命」を後悔したことは一度もないと言い切った。
実は同じ問いを、この小さな旅で出会ったほとんどの人に投げかけていた。あれだけの流血と犠牲を払ったにもかかわらず、現状が「革命」以前と何ら変わらないか、もしくは悪化すらしたと思うのなら、三年前の「革命」を後悔しているはずだ、と。つまりは徒労以下ではなかったのか、と問うたのだ。しかし、どんなに現状を嘆き、革命青年たちや同胞団を非難した人でも、「後悔している」と答えた人はほんの数えるほどしかいなかった。
「革命はすばらしかった」
そのひと言を口にするとき、人びとは当時の自分の気持ちをどこか慈しむような表情さえ浮かべた。
あの「革命」で得たものはあったのか。そう尋ねると、ラグダはしばらく考えて「あの日からエジプト人たちは変わった。エジプト人であることを誇りに思えるようになった」と、少しためらいがちに話した。
意外な台詞だった。同時にその言葉を聞いた途端、それまでの数日間、首を傾げっぱなしにしていた違和感のようなものが、私の中で氷解していった。
――別れ際、もうひとつだけ質問した。希望的観測が事実を歪めてはならないと自制し、敢えて「新たな軍政は盤石で、もう希望など抱けないのではないか」と問うてみた。
彼女は川面の光に目をやりながら、しばしの無言の後、こう答えた。
「そう、状況はとても厳しい。厳しいけれど、不可能ではないはずよ。その行く末を決められるのは私たちしかいない。私たちはこの三年で、人として強くなったと思う。でも、まだきっと足りないのでしょう。だから、もっと強くならなければならない。生きている間、あと一度だけでもいい。あの三年前の美しい日を見てみたい」
その声は少し震えていた。















