文脈が読めないがゆえに、全て自分に都合よく見えてしまう、お粗末な「反ポストモダン」脳―「disる/disらない」の単純二分法でしか考えられない山川ブラザーズの壮大な陰謀論
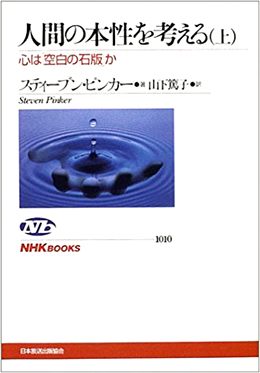
スティーブン・ピンカー『人間の本性を考える―心は「空白の石版」か』(NHK出版、2004年)
前回 [2]の連載がアップされた少し後、安直な“ポストモダン”批判を繰り返すことでネット上で目立とうとする山川賢一が誰かに入れ知恵されたらしく、この連載での私の記述に関して、「致命的な間違いがある」、「仲正の方こそテクストを読んでいない」、「嘘八百を並べ立ててい る」、「捏造だ」、などと騒ぎ始めた。実際には、私がある箇所で多少端折った言い方をしたことを、彼が、大げさに、かつ、かなり曲解し、鬼の首を取ったつもりになって、空騒ぎしただけである。私の書き方に多少難があったかもしれないと思えるのは、基本的に一か所、多くて二か所で、それらの箇所も文脈をちゃんとフォローできる人が読めば、どういう意図かはっきり分かる内容である。それ以外の点は、本の読み方を知らない山川の妄想の産物である。
しかし山川は、私の“致命的弱点”を見つけたと思って有頂天になったのか、私がどうリアクションするか不安でしかたなかったのか、あるいは、彼自身の人生の見通しが真っ暗でやけになっていることの反映か、ほとんど同じ内容を二十日前後にわたって、ツイッターやブログで連投し続けた。すると例のごとく、uncorrelated、「yono@iyono」「AQN@ヮ<)ノ◆」「Holm @holm239」「ほしみん@hoshimin」、「佐野剛士@akumatengoku」 「沼津圧倒的成長部@3日目・東6セ-12b」、 といった自分でテクストを読む能力のない連中が、山川の言い分を鵜呑みにして、訳が分かっていないくせに、私に対する誹謗中傷に加わった。まさに山川ブラザーズである。勝手な妄想によって随所で話を捻じ曲げて、内輪で盛り上がっている山川ブラザーズにわざわざ反論するのは無意味なことだが、学校で本の読み方をちゃんと習わなかった奴がどのように妄想を積み上げていくのを示している、いい例なので、以下主だった点についてコメントしておこう。
山川ブラザーズが捏造だと言って一番騒いでいるのは、この連載の第四十二回 [3]でのアメリカの認知心理学者スティーヴン・ピンカーについてのちょっとした記述である。ブラザーズは、「ピンカーは激しくポモ批判しているのに、仲正はほとんど批判していないように捏造している。仲正はそういう捏造をせざるを得ない所まで、追いこまれている!」、と主張する。出だしから間違っている。私は別にピンカーの主張が、「ポストモダン」思想にとっても、私個人にとっても脅威であるなどとは一切感じていないし、感じなければならない理由などない―― どうしてそう言えるのかについては、以下で述べていく。山川がしつこく、「ポストモダンは、ブランク・スレート説に依拠している。ピンカ ーなどの議論によって、ブランク・スレート説が無効であることが明らかにされ、欧米ではポストモダンはすたれつつある」、などと適当なことを言い続けるので、その適当さを指摘しただけである。ピンカーの議論が、「ポストモダン」系の思想にとって脅威だからではない。
山川ブラザーズは全然理解していないようなので――無駄と承知で――第四十二回で述べた、私の基本的立場をもう一度確認しておこう。ピンカーはその著書《The Blank Slate》 (邦訳タイトル『人間の本性を考える』)で、「心はブランク・スレートであるという教義は、人間についての研究をゆがめ、ひいてはそうした研究をよりどこ ろにして下される判断を、公私を問わずゆがめてきた」(邦訳より引用)と述べている。彼によると、「私たちの社会の主流の知識人 our intellectual mainstream」はこの教義に従っている、という。そして第一章の冒頭部で、英国の哲学者ジョン・ロックのブランク・スレート説を核とする経験論に触れ、ブランク・スレート説のインパクトによってそれまでの身分制社会が根底から揺るがされ、「前世紀には、ブランク・スレートの教義によって、多数の社会科学や人文科学の路線が設定された」などと、ブランク・スレート説の影響の大きさを強調している。
こうしたピンカー の議論の前提になっている部分をごく素直に読めば、ピンカーは、英国経験論の影響を受けた社会科学・人文科学全般の在り方を問題にしており、少なくとも 「ポストモダン」だけを問題にしているのでないことは分かる。英国経験論の大前提に問題があるとすれば、当然、その後継者である英米系の哲学のほとんどが批判の俎上に載せられることになる。思想史的にオーソドックスな見方をすれば、経験論の直系は、「ポストモダン」とむしろ対立関係にある分析哲学である。実際ピンカーは、ブランク・スレート説を広めるのに貢献した哲学者として、ジョン・スチュアート・ミルやバークリー、ギルバート・ライル、ヒューム、カント、サルトル、ニーチェ、ヴィトゲンシュタイン、ゴドウィン等を挙げている。この中には、明らかに「ポストモダン」と対立する考え方をしている人が含まれている。山川やuncorrelatedは、 「いや、ピンカーの『ブランク・スレート』説批判はもっと現代的な議論を念頭に置いている」とか、「経験論系の哲学者でも好意的に評価されている人がいる」、などと言って、私に反論したつもりになっているが、見当外れである。ピンカー自身が「ブランク・スレート」説と、英国経験論の繋がりを指摘している ――常識的な話なので、別にピンカーに教えてもらうまでもないことだが――のだから、基本的に、経験論の系譜を引く哲学全般が彼の批判の俎上にのるはず だ。私は、そういう当たり前のことを書いたのだが、山川ブラザーズにはそこからして理解できないようである。
ピンカーの中では、典型的なブランク・スレート説でないので、経験論の系譜に属していても好意的に評価できる哲学者もいるということになっているのかもしれないが、何が彼にとっての許容範囲の基準になのかはっきり分かるような書き方をしていない。場面ごとにアド・ホックに使い分けているのだとすれば、思想史の記述としてはダメである。真面目に思想史を勉強している人間であれば、どうして「ブランク・スレート」などという大げさな概念を掲げて、西欧近代の文系学問の“主流派”なるものを批判しようとするのか、藁人形ではないのか、という疑問を持つ。思想史に全く興味がなく、ピンカーを妄信する「ほしみん」は、「ピンカー先生がいい加減なこと を書くはずがない、ピンカー先生が藁人形論法を使っていると主張する仲正の知的怠慢は眼を覆うばかりだ」、などと聴いた風なことをツブヤイテいた。これほど短絡的で認知バイアスの塊のような奴が、ピンカーをちょっと読んだだけで世の中の全てを分かった気になり、論客ぶって現役の学者である私を罵倒するのであるから、呆れかえる。
ピンカーは心理学者であって、思想史家も哲学者でも社会学者でもない。だからピンカーや彼の信者に、「ブランク・スレート」のレッテルを貼られたからといって、(「ポストモダン」系とされる人も含めて)文系の学者が怖れる必要はない。心理学と文学や哲学、社会学では、扱う対象や方法論が異なる。この点もちゃんと書いたのだが、ブラザーズは理解していない――だから、「仲正が脅威を感じて捏造によって、ピンカーの批判を回避しようとしている」、などという頓珍漢な妄想を展開することになる。“ピンカーの批判”を真剣に受けとめる必要があるとすれば、当該の哲学、文学、社会学などの理論が依拠している大前提、公理のようなものが、単に字面のうえだけでなく、実質的に「ブランク・スレート」仮説に依拠しており、それが心理学なり認知科学によって実証されている科学的事実に反している場合である。 ピンカー先生が、「〇〇の理論はブランク・スレート説的だ」と漠然と示唆するだけであれば、単なる個人的印象なので、気にする必要はない。ここが肝心だ。
『人間の本性を考える』の中に、確かにポストモダンについての批判的なニュアンスの言及はある。私は、ピンカーがポストモダンを批判していない、などとは言っていない。上 に述べた意味で、具体的論拠が乏しい、と言ったのである――山川等はそれが理解できない、あるいは、強引に揚げ足を取ろうとして無視している。ポストモダン系の思想と「ブランク・スレート説」の関係について、単なる皮肉のような話ではなく、ある程度明示的に述べられているのは、(日本語訳の区分けで)第二十章「芸術」だけである。この章でピンカーは、現代のエリート的な芸術運動では、美に関する人間の感性をめぐる「ブランク・スレート」的な考え方が支配的になっており、それを主導しているのが、ポストモダン系の理論である、という主旨のことを述べている。モダニズムやポストモダニズムは、「まちがった人間心理の運動であるブランク・スレート説にもとづいている」と述べられている。Viking Pressから出ている原典だと、四一二~四一三頁、邦訳だと下巻の二五〇~二五三頁にかけてである。この肝心のところで、ポストモダン系の特定の理論家の具体名は出てこない。
私はそのつもり で、四十二回目の連載で「ポストモダニストの具体名を挙げているわけではない」、と書いたのだが、山川と彼に入れ知恵した人間はここに食いついてきた。確 かにこの言い方だと、全巻を通じてポストモダニストの名前が一切出てこない、と言っているようにも見える。少々雑な書き方だったという気もするが、ちゃんと筋道を追って考えられる人が読めば、「ブランク・スレート説に明白に基づいた芸術論を展開しているポストモダニストの具体名を挙げていない」、というつもりなのは十分分かるだろう。それに、ポストモダニストの名前が出てくるかどうかは元々大した問題ではない。先に述べたように、個々の理論家が、(生物学・心理学的な意味での)「ブランク・スレート説」に明白に基づく理論を展開している、という論証がない限り、ほとんど意味がない。しかし山川ブラザーズは、名前が挙がっているかどうかが重大問題だ、と思い込んでしまって、私が捏造したと大騒ぎし始めた。そして他にもないかと強引なあら捜しを始めた。基本的にはそれだけの話である。
山川等がポストモダニストの具体名が出ているじゃないか、と大騒ぎしている箇所に、どれほどのことが書かれているか一応述べておく。日本語訳にはないが、原典には人名を含んだ索引があるので、簡単に確認できる。二十章には、フーコーとバトラーの名前が二回出てくるが、一か所は、ポストモダニズム系の批評の流行がアドルノやフーコーからバトラーに移ったらしいということと、そのバトラー論文が悪文コンテストの一等賞に選ばれた、というしょうもない話を紹介しているだけ。もう一か所はその少し後で、これまた、「最近の大学院生はフーコーやバトラーといった権威者の名前を適当にばらまいたちんぷんかんぷん(in gibberish)の文章を書かないかぎり就職市場が締めだされてしまう」、という個人的な印象を述べているだけである。無論、具体的統計資料とか当事者へのインタビューとかを示しているわけではない。山川たちには、これがものすごく意味のある学術的な言明に見えるようだが、単にdisっているというレベルの話だ。
山川は得意気に、別の章にデリダとバルトの名前が出てくる箇所があると言っているが、ここもそれほど大したことは言っていない。第十二章「人は世界とふれあう In Touch with Reality」の中で、言語が世界を決定するという考え方が言語学だけでなく、社会科学でも強まっていると述べられている。その関連で、「脱構築主義やポストモダニズムをはじめとする相対主義」の教義の例として、この二人が引き合いに出されている。デリダについては、「言語から逃れるのは不可能である」「テクストは自己言及的である」「言語は力だ」「テクストの外には何も存在しない」といった文が彼に由来するものとして参照されているが、これらは正確な引用ではない。最後の一つ以外は、本当にデリダ自身の主張と言えるのか怪しい――最後の一つも、デリダがかなり特殊な意味で「テクス ト」と言っていることを知らないと、誤解する。実際、ピンカーは、引用元を明らかにしていない。し かも、これらがどういう意味で「ブランク・スレート」説に依拠していると言えるのか全く説明していない。何となくデリダっぽいと思われる文を並べて印象付けただけである。バルトについては、一応引用元――バルトの主要著作からではなく、あるシンポジウムでの報告の一節である――を示したうえで、「人間は言語以前には存在しない、種としても個人としても」という文が引用されているが、デリダの場合と同様、これがどういう意味で言われているのかについての説明 はない。山川や「ほしみん」には、こういうのが学問的に厳密で信頼に値する“批判”に見えるのだろう。
因みに山川は名古 屋大学の大学院でバルトを研究していたはずだが、彼はバルトがピンカーが言っているような、生物学・心理学的な意味での「ブランク・スレート」説を取っていると考えているのだろうか? もしそれが立証できるなら、バルト研究にとって画期的な意味を持つはずなので、是非論文にすべきである。かつての彼の恩師や、専門のバルト研究者の人たちから見直してもらえるだろう。何かの有益な仕事に繋がるかもしれない。それとも、いつもの調子で、ピンカーの一行にも満たない引用で十分証明になっていると言い張って、終わりにするのだろうか?
uncorrelatedは、「ピンカーはポストモダンは精神を腐すと言っているが、大してポストモダン批判はしていない by 仲正昌樹」というへんてこなタイトルのtogetterを開設して、そこに山川等のツイートを貼り付けて、得意になっている。この男も、学問的な意味での「批判」という言葉の意味を知らないのだろう。こういう連中は、学問からドロップアウトして当然だ。ただし、「大して」を「大した」と訂正するのであれば、大筋で、私の発言と認めてやってもよい。
この前後の山川等のツイートを見ていると、彼らはテクストを読む時、何が全体的な主題になっているのか、どういう文体がどういう狙いで採用されているのか、どのような論拠に基づいてどういう論証がなされているのかといった肝心なことはどうでもよくて、もっぱらその著者が、〇〇をディスっているか/いないか、ということにしか関心がないようである。普段から反ポモ的な態度を取っている思想家や文学者のテクストに、ちょっとでも「ポストモダン」を暗示しているような表現が出てくると、そのテクストは「反ポモの書」ということになってしまうようである。
第二点に移ろう。山川は、同じ第四十二回の「サイエンス・ウォーズ(ソーカル事件)に登場したソーカル、ブリクモン、ブーヴレスや、ポスト・ソーカルの論客としてよく引き合いに出されるジェイムズ・ロバート・ブラウンなどは、(中略)狭義の“ポストモダニスト”と、(中略)ファイアーアーベントやラトゥール等の批判的科学社会学者を一括りに“ポストモダニスト”と呼んでいる」、という言い回しにかみついて、「嘘だ! ブラウンはポストモダニストと社会構築主義者を区別している!」、と吠えている。これは山川が「区別」という言葉の意味を知らないことを端的に示している。
『なぜ科学を語ってすれ違うのか』(《Who rules in science》, Cambridge University Press, 2001)で、ポストモダンと社会構成主義の関係について述べられているのは第四章であるが、この章の冒頭でブラウンは、「ポストモダン主義は、社会構成主義のなかでもニヒリズム寄りの一翼をなし、社会構成主義全体としてみればかなり特殊な集団といえる」(邦訳、一三四頁)と述べ、社会構成主義――社会構築主義とも訳される――(social constructivism)の中の最過激派、あるいは、その内部の特別な変わり者として位置付けている。その後で、社会構築主義の中の自然主義派(naturalistic versions)とポストモダン主義が対立していると述べているので、“区別”をしているようにも見えるが、そもそも、社会学の方法論、あるいはそれを重視する流派である「社会構成主義」の中に、哲学、文芸批評、精神分析、文化人類学などを出発点とするポストモダン系の思想を位置付け ること自体が思想史・学問論的におかしい。社会構成主義の立場に立つ「科学社会学」というのはあるが、“ポストモダン”にはそのような部門はない。そもそもこの連載でずっと述べてきたように、「ポストモダン」学と呼べるような統一的な集合体も、思想的な共通の前提も、方法論もない――この連載の二十二回~二十四回(拙著『FOOL on the SNS』 [4]=明月堂書店刊=に転載)、及び、四十一回以下を参照。
更にこの四章では、ポストモダン批判の延長で、社会構成主義のニヒリスト的な極に位置する人物としてファイアーアーベントが取り上げられている。ファイアーアーベントは、狭義の社会構成主義者ではないし、“典型的なポストモダニスト”としてやり玉に挙げられることの多いデリダ、ドゥルーズ、リオタールなどとはかなり異質な思想の持ち主だが、これでは、ファイアーアーベントがポストモダニズム系の科学論の代表格のように見えてしまう。私はそういうことを「混同」と言ったのであるが、山川等の雑な思考では、社会構築主義者の一部がポストモダニストと対立しているという書き方をすれば、両者を十分に区別したことになるのかもしれない。
第三点として、やはり四十二回の記述に関する、山川の意味不明のクレームも紹介しておこう。山川がピンカーと並ぶ「ブランク・スレート」説批判の大物として持ち上げているE・O・ウィルソンについて、私は以下のように述べた:「「社会生物学」という七〇年代に登場した比較的新しい分野の研究者である。創始者は彼自身である。人間を含む生物の社会的行動全般を研究対象とするこの分野は、生物学の他の分野に比べて、直接的に実証できないファジーな部分が大きい。だから、ウィルソンの議論を契機として「社会生物学論争」が起こった。論争の当事者になるような先鋭的な議論をする人を、生物学の代表のような形で引き合いに出すのはミスリードである」
これに対して、山川は、この連載四十一回 [5]での私の発言を引き合いに出して(いるつもりで)、「仲正は論争に意味はないと言ったのに、論争の有無を問題にしている。矛盾していることに気付かないんですかね。失笑してしまいます」、という主旨の恐ろしく頓珍漢なツイートをしている。第四十一回の記事をまともな人間がちゃんと読めば分かるように、私は「論争に意味がない」と言ったのではなく、「論争の勝ち負けで思想のブームが決まるなどと思っているのか?」と言ったのである。山川や祭谷一斗、ほしみん、佐野剛士等の頭の中では、これが同じことになってしまうようである。ここまで思考回路が狂っている人間には、何を言っても意味は ないだろう。山川 は更に、「仲正は論争に意味はないと言ったが、俺は論争に意味があることを示す。論争でのウィルソンの勝利によって、社会生物学会が誕生したのがその証拠だ!」、と理解不可能な“論”を展開していた。
第四点として、前回(第四十七回)の記述に対する、山川のクレームを取り上げよう。この回において私は、山川がネット上でぶっきらぼうに投げかけた、以下の“質問”に対し てコメントしている。山川の“質問”というのは、彼がネット上で見つけてきたらしい、デリダの『哲学の余白』の以下の部分に関するものである。
「差異はトポス・ノエートス(叡智界)のなかに書き込まれているのでもなければ、あらかじめ脳髄の蝋板に書かれているのでもない。(中略)ただ諸差異だけがそもそものはじめから徹頭徹尾「歴史的」でありえるのだ」
山川が『哲学の余白』に収められている当該の論文全体を読まない――あるいは、理解しない――まま、この断片からの印象だけで、デリダは「ブランク・スレート」説だと強引に決めつけ、それをどう思うか、と私に“質問”――実際には、質問というより、意見の押し付けである――したのである。私が、どう“答えた”かについては前回の記事を見て頂きたいが、その中で私は、「蝋」という譬えは、物質をめぐるデカルトの議論を念頭に置いているものだろう、と述べた。そのことに関して、山川は「ある知人」から教えてもらった情報を基にして、「これも嘘八百。デリダも草葉の陰でびっくりしているだろう。元ネタは、デカルトではなくアリストテレスだ」という調子で、私を罵倒した。そして、その知人から教えてもらったというジョルジュ・アガンベン――正しくは、ジョルジョ・アガンベン(Giorgio Agamben)――の著書の以下の一節を引き合いに出した。
…『霊魂論』第三巻に見られる一節である。アリストテレスは其処で、ヌース、つまり潜勢力という状態にある知性ないし思考を、まだ何も書かれていない書板に喩えている。 『書板(グランマティオン)が、現勢力という状態にあっては何も書かれていない(が、潜勢力という状態にあっては字が書かれていると言える)のと同様のことが、ヌースについても起こる』。紀元前4世紀のギリシアでは、パピルスの紙の上にインクで書くというのは、唯一の通例の書き方ではなかった。薄い蝋の層で覆われた書板を尖筆でひっかいて書くというのがより普通であり、特に私用ではそうだった。自分の論考の決定点に至り、潜勢力という状態にある思考の本性と、思考が知性の現勢力へと移行する在り方とを探求するときに、アリストテレスが例として用いているのがこの種のものである。恐らくそれは、彼が自分の思考のあれこれをその瞬間に書き留めていた当の書板自体だったのだろう。(『バートルビー 偶然性について』、p11-12)
この一節を見て、私も最初、「トポス・ノエートス」というプラトン的な表現の直後なので、その対比として、アリストテレス由来の比喩を使っているという考え方もありかと思い、山川に知恵を授けた「知人」に一定の敬意を表してもいいという気はした。しかしデカルトではなく、アリストテレスだと言い切るには論拠が弱い。また、 “ポストモダン”と私を貶めたいという山川の悪意と混乱のせいで、全体的に恐ろしくねじ曲がった話になってしまった。どうして、山川のような訳の分からない奴ではなく、私に直接言ってこなかったのか?
まず、最初に確認しておくべきこととして、当該論文の中でデリダが「脳」に言及しているのは、先の一文だけである。当然、「蝋(板)」の比喩もこの一か所しか出てこない。 言語体系を言語体系をたらしめている「差異」は、叡知界にも、脳という物質の中にもない、というごく当たり前のことを確認するために、「脳」とか「蝋」という表現が出てくるにすぎない。山川は、この箇所のちょっと後に、「意識」という言葉も出てくるので、やはり認知科学的な話のはずだ、と言い張っているが、論文全体を読めば、この「意識」というのも、認知科学的な意味で言っているのでないことはすぐ分かる。先に述べたように、山川は自分に都合がよさそうなキーワードを一つでも見つけると、その本や論文全体がそのキーワードをメインテーマにしていると思い込んでしまうようだ。一か所でしか使われていない比喩の「元ネタ」を云々するのは無意味である――それとも、山川は「元ネタ」という言葉を通常とは異なる意味で使っているのか? 哲学でも文学でも「蝋」という比喩はいろんな文脈で使われているので、誰のどのテクストをより強く意識しているか、という蓋然性の話でしかない。複数の著者、テクストを念頭に置いていても、全然おかしくない。アリストテレスとデカルトを同時に念頭を置いていることは十分にありうる。そこを理解しないで、比喩の“正しい元ネタ”を決めようとする山川は見当外れである。
デリダは、単なる比喩とか注釈にしか見えないものの中に重要な意味が隠されていることを明らかにしていく脱構築的読解の名人だが、さすがに、当該テクストにたった一回しか登場しない――他の比喩と有機的に連関しているわけでもない――比喩だけを根拠に、「この比喩が使われている以上、このテクストのテーマは〇〇だ」、などと主張したりしない。それは読書が苦手なくせに、分かったふりをしたがる中高生がやることである。
このことを踏まえたうえで、アガンベンが上記で参照しているアリストテレスの『霊魂論』の該当箇所を、デリダが『哲学の余白』の記述の中で強く念頭に置いていたとする、山川の「知人」の意見について検討してみよう。先に述べたように、プラトンの後にアリストテレスが来る蓋然性は高いと言えるだろう。「魂」と「書板」という 比喩が、「脳」と「蝋板」という比喩にシフトしたという見方にもそれなりに説得力はある。ただ注意する必要があるのは、アリストテレスはあくまで、「魂」 と「書板」について述べているということである。「魂」と「脳」を連想で結び付けるのは近代人の発想であって、古代ギリシア人であるアリストテレスの発想ではなかろう。無 論、近代人であるデリダが、「魂」を「脳」に置き換えてイメージした可能性はあるが、デリダがアリストテレスを強く意識しているとすれば、その置き換えについて何らかの説明・弁明をしている、あるいはヒントを与えているだろう。また、アガンベンは、アリストテレスは『霊魂論』の該当箇所で、〈grammateion(書板)〉ではなく、〈epitedeiotes(蝋膜)〉と書くべきだったと述べているが、それはアガンベンの解釈であって、アリストテレス自身の使っている表現は、あくまで〈grammateion〉である。「蝋」とストレートに結びつくわけではない。
それから、これは日本語訳だけ見ていると分からないことだが、原文でデリダが使っている言葉は、〈cire(蝋)〉であって、〈tablette de cire(蝋板)〉ではない。「板」という言葉が入るか入らないかで、かなり印象が異なる。〈cire〉という一つの単語で表現されているので、私は、叡知界との対比で、脳の物質性を強調するためだけの比喩と理解し、デカルトの物質論からの連想だと判断したのだが、既に述べたように、そこにアリストテレスの「魂=書板」のイメージも被さっていると認めることにやぶさかではない。ただ、デリダはそのことを特に 強調していないのは確かである。アリストテレスのことを強く示唆したいなら、ギリシア語の原語を挿入したり、アガンベンがやっているように何か暗示的な “注釈”を挿入しているだろう。当たり前のことだが、デリダはアガンベンではないので、アガンベンの関心とデリダの関心が常に一致するわけではない。『グラマトロジーについて』とか『プラトンのパルマケイア』など、「書字」をメインテーマにしたテクストであれば、『バートルビー』でのアガンベンの関心と、デリダのそれがかなり重なっていると見てよいが、『哲学の余白』の該当論文はそういう性質のものではない。
百歩譲って、デリダがアガンベンと同じ様に、該当箇所で、「魂」と「書板(蝋板)」を結び付けるアリストテレスのメタファーに対する強い関心を示していたとしても、それは、ピンカーの言う「ブランク・スレート」説とは関係ない。アリストテレスは、知性の可能状態(dynamis)を「何も書き記されていない書板(grammateion)の状態」に譬えているが、これは「終極実現状態(entelecheia)」との対比で使われている表現であって、ロック以降の経験論で問題になっている基本概念の生得性の有無とは関係ない。これは『霊魂論』の該当箇所の前後を読めば、分かることである。
アガンベンは、アリストテレスのメタファーが〈tabula rasa〉という後代の哲学的メタファーの起原であることを指摘しているが、彼自身は別に「ブランク・スレート」説の話をしているわけではない。小説の中のバートルビーの振る舞いと職業が、「蝋板」をめぐる比喩と結び付いている、という話をしているだけである。これは、アガンベンによる評論か、小説『バートルビー』のいずれかを読んでいれば、簡単に分かることである。山川の「知人」は一体彼に何を教えてやったのだろうか? ――山川や「ほしみん」「佐野剛士」のような精神状態を「ブランク・スレート」と呼ぶのであれば、アガンベンはある意味、「ブランク・スレート」について語っていると言えるかもしれない。
結局山川は、デリダがテクストの中で一回だけ使っている比喩が、[tabula rasa→blank slate]という比喩と語源的に重なっているかもしれないという話を、「デリダ=ブランク・スレート」説という大風呂敷な妄想にまで広げてしまったのである。彼は、 名古屋大学でテクストの読み方について何も学ばなかったのか? その山川を大学教授の知的怠慢を暴露する論客として持ち上げる「ほしみん」や佐野剛士、(自称医療ジャーナリストの)祭谷一斗などはどういう教育を受けてきたのか? 彼らにとって、「ブランク・スレート」説とは何なのか?
これと関連した、山川のもう一つの誤読も最後に指摘しておこう。山川は、「知人」からピンカーやアガンベンについて入れ知恵される前に、以下のようにツイートしている。
仲正先生からお返事をいただきました。山川はデリダの哲学的議論を認知科学の枠組みにおしこめ曲解しているとの主張ですが、ぼくがいった、差異の有無を判断する基準が先天的に存在していなかったら帰納的推論できないってのはクワインの主張なんで、こっちも哲学的議論なんですけど……
クワインそのものは読んでいないけど、丹谷先生の本でそういう議論を知った。
人間はブランクスレートか否かってのは哲学的議論でもあるから、認識論の自然化とか哲学の自然化という話が出てきているのだと思っていたのですが。仲正先生は「ブランクスレートか否かは科学的問題! デリダは哲学的議論をしてる! 関係ない!」という切断操作をしたがっているようにみえますが。
これも例によって、山川流の曲解と誤読の組み合わせである。哲学者の中にもデネットのように、認知科学的な次元での議論にコミットしている人はいるが、デリダはそういう次元の議論にはほとんど関与していない。哲学にもいろんな分野、議論の次元がある。哲学者が「自然科学」に関わる議論をする場合でも、個別分野の研究内容に立ち入った議論をする場合もあれば、メタ・レベルでの検討を加えるだけの場合もある。「ブランク・スレート」説は哲学の問題か、などという雑な問いに意味はない。
因みに、山川が読んだクワインに関する本というのは、『現代思想の冒険者たち』に入っている、(丹谷ではなく)丹治信治氏の『クワイン』のことだが、この短いツイートからも山川が、(かなり漠然とした意味での)「ブランク・スレート」説が哲学の主要な問題であると主張せんがために、かなり強引な理解をしていることが窺える。先ず、クワインが言っているのは「差異」ではなく、「類似性」である。「差異」は「類似」の裏返しにすぎないと言うかもしれないが、デリダは「差異の体系」としての「言語」における「戯れ」について論じているのだから、「差異」と「類似」でかなり話が違ってくる。デリダとクワインはいずれも「言語」を問題にしているものの、切り口や議論の次元がかなり異なる。「差異」と「類似」を混同したりすると、余計話がかみ合わなくなる。
この点を大目に見るとしても、「差異の有無を判断する基準が先天的に存在していなかったら帰納的推論できないってのはクワインの主張」だというのは、かなり怪しい。丹治氏の本の該当箇所を読めば分かるが、山川は「帰納的推論の正当化」と、「帰納的推論」それ自体を混同しているようである。その違いも大目に見て、クワインが「帰納的推論」が「類似性」に関する生得的感覚に基づいていると主張しているとしても、だからといって、クワインが反 「ブランク・スレート」説の立場を取っていることにはならない。繰り返し述べてきたように、「ブランク・スレート」説というのがそもそも、どういう説なの か具体的に特定しないと、意味を成さない。山川――あるいは彼に入れ知恵してやった人間――は、丹治氏の 本の二四九~二五〇頁だけ見て分かった気になったのだろうが、この部分で説明されていることは、クワインの思想のごく一部でしかない。プラグマティズムの系譜に連なるクワインは、どちらかと言うと、言語の社会的・歴史性格を重視する哲学者である。丹治氏の本の全体を読めば、あるいはせめて二四九~二五〇頁だけでなく、二五一頁までちゃんと読むと、「ブランク・スレート」説でクワインを引き合いに出すのは筋がよくないと分かるはずだ。クワインにせよ「ポストモダニスト」にせよ、哲学者のほとんどは、人間の精神は生得的に形成されている部分と、個人的経験や社会の影響で構築される部分の両面があるという前提で議論をしているので、「ブランク・スレート説」というのが何の生得性を否定する説なのか特定しないと、意味を成さない。
最後にもう一点、山川の根本的な勘違いを指摘しておこう。前回の私の記事に関連して、山川等は、ポストモダニストは普段から過激なことを言っているくせに、批判されると、自分たちの言っていることはそんな大それたことではない、もっと常識的なことだと下手な言い訳する、などと分かった風な口をきいていた。そういう風に見えるのは、ほとんどの場合、反ポモを標榜している人間が、 “ポストモダニスト”のテクストで語られていることを理解していない、あるいは、読まないで“批判”しているからだ。
先にデリダに即して述べたように、“ポストモダニスト”と呼ばれている人の多くは独自の視点からのテクスト読解や表象分析によって、常識だと思われていることに前提として潜んでいる、思いがけない不思議な事態、関係性、意味の層を掘り返し、そこから常識に揺さぶりをかけることを得意とする。常識自体の中に潜んでいる矛盾を起点にして思考を進めるというのは哲学や文芸批評の常套手段が、“ポストモダニスト”はそれを標準とはかなり違うやり方で遂行するので、その道のプロでもびっくりさせられる。しかしよく読めば、ちゃんと筋道が通っていることが多い。最初から最後までちゃんと読まないで、結論だけ読むと、訳が分からないとか、やたらに非常識、といった雑な印象しか残らない。無論、“ポストモダン”を気取って、外見だけ派手で、本当に無意味な文章を書くライターもいるが、それは、ちゃんと読んだうえでないと判断できない。山川ブラザーズのように、「おお! ソーカル大先生がラカンをすごくdisっている!」「ピンカー大先生はバトラーもdisっているぞ!」「ブラウン先生はデリダをdisっている! ポモはとうとう追い詰められた!」、などと、下手な八百屋政談のような話で盛り上がっている輩には、“ポモ”が本当は何と言っているのかなどどうでもいいのだろう。
“ポモ”の話と直接的関係ないが、山川ブラザーズには、頭の中がどうなっているのか本当に不可解な奴が多い。「yono@iyono」と「AQN@ヮ<)ノ◆」は、拙著『Fool on the SNS』 に所収の「アニメ・アイコン」に関する記事(連載第五回)に関する、ある人のツイートの内容と、今回の山川の妄想めいた言いがかりを短絡的に結び付けて、
「『アニメアイコンが〜』しか、言い返す所なかったんですねえ>仲正先生(;´д`)」(yono@iyono)
「仲正昌樹って人、しんかいさんに発言のデタラメさを叩かれて、逆恨みして「これだからアニメ・アイコンは」なんて2017年にもなって言ってるのか。痛い人だな」(AQN@ヮ<)ノ◆)
などと、時間的前後関係が全く逆のデタラメな話を作って、悦に入っていた。
もう一人単純なバカのサンプルを挙げておく。連載第四十一回で指摘したように、いきなり私に対して“ポモ”関連の誹謗中傷を連投したあげく、自分の方が被害者であるかのごとく装った「たかはし@調布圧倒的成長部@tatarou1986」という奴がいる。山川はこいつに便乗する形で、私に対する誹謗中傷を始めたのである。「たかはし」はその後、「ネット論客などやめてやる!」と宣言して、ハンドル名も、「沼津圧倒的成長部@3日目・東6セ-12b」と改名していた――前にもまして、どういう精神状態なのかと思わせる、異様に長いハンドル・ネームだ。その「たかはし」が、八月上旬の山川の連投に刺激されたのか、以下のような誹謗中傷ツイートをしている。
あの人とメールしましたけど、仲正が「学術的作法では、これこれこうなるんだよ」などという説明してくれたことはないですね。被害妄想全開で、こちらの一挙手一投足をすべてポモへの攻撃だとみなして曲解するんです。正直私は彼の精神状態に不安があります。
こいつも山川と同じで、自分がやったことは全て忘れ、自分は紳士的に振る舞ったのに、一方的に攻撃された被害者だという記憶に簡単にすり替えてしまうようである。自分自身の「ネット論客廃業」宣言も忘れたのだろう――「たかはし」が実際、どのように振る舞ったかは、第四十一回を参照。私の精神状態を不安に思うと言っているが、それはこいつ自身の抱えている不安の投影だろう。ごく常識的に考えて、学者・教師としていろいろ忙しく日々の仕事をしている私と、こんなおかしなハンドル・ネームを付けて一日中無意味なツイートを続け、自分がネット論客廃業宣言をしたことも忘れ、頼まれてもいないのに争いごとに首を突っ込んでくるこの男のどちらの状態がより不安定だろうか?
山川はとにかく私が追い詰められていることにしたいようだが、一体、何によってどのように追い詰められていると思っているのだろうか? ポモが衰退したことで、大学でのポストを失う恐れが高くなったということか? それとも著作の出版や学外での講演などの仕事ができなくなるということか? いずれも、私自身にはほとんど実感がない。それとももっと別のすごいシナリオを考えているのか? 山川ブラザーズによる、ソーカルやピンカーの受け売りの受け売りの受け売りの……受け売りは不毛であり、かなり飽き飽きしているが、彼らが、“ポモ学者としての仲正が追いつめられている状況”なるものを、どう想像しているかについては多少興味がある。私が全く想像できなかったような面白いストーリーを考えて披露してくれるのであれば、誉めてやってもいい。

■仲正昌樹=著
■定価:本体1800円+税
■判型:四六判
「極北」誌上連載の単行本化第1弾!
|
『FOOL on the SNS』発売にあたりまして、本著に収録した仲正昌樹氏の連載記事中1~36回分を2017年8月1日付で「極北」ブログサイト上では非公開とさせて頂きました。閲覧ありがとうございました。
|

